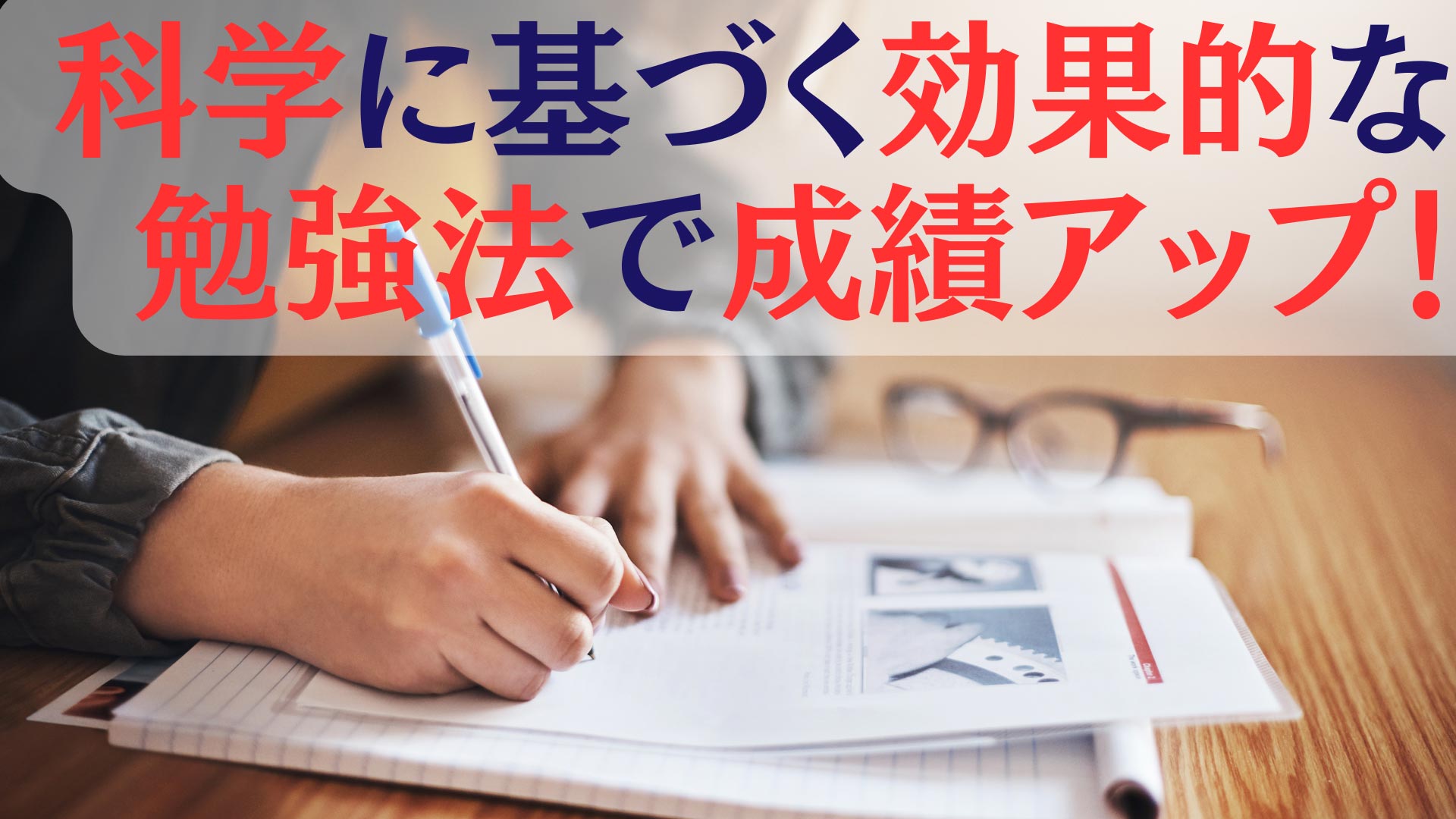ヒューバーマン博士の知見から学ぶ学習法
今回の記事では、脳科学者でありスタンフォード大学医学部の教授でもある アンドリュー・ヒューバーマン博士 の研究を参考にしています。ヒューバーマン博士は、やる気や集中力、学習効率を高めるための実践的な方法について、多くの研究と発信を行っています。その知見をもとに、勉強へのやる気を引き出し、成績向上につながる様々な方法を分かりやすく解説します。
本記事では、スタンフォード大学のヒューバーマン博士の研究を参考にしています。博士の詳しい解説はこちらのYouTube動画でご覧いただけます。
苦しい」は「伸びてる」のサイン?科学が解き明かす本当の学習法
はじめに
勉強と聞くと、「つらい」「難しい」「我慢」といったイメージが先行しがちです。しかし、最新の認知科学研究が示しているのは、意外な事実です。それは、学習中に感じる「ちょっと難しいな」「なかなか思い出せないな」という適度な困難、いわゆる「望ましい困難」こそが、脳を最も成長させるという新常識です。
これは、学習が単に知識を頭に「入れる」作業ではないからです。むしろ、一度覚えた情報を脳から「引き出そう」と奮闘し、間違いを修正するプロセスそのものが、脳の神経回路を強化し、記憶を盤石にするのです。
この記事では、その「望ましい困難」を意図的に作り出し、学習効果を最大化するための科学的な学習法を5つのポイントに分けて、具体的かつ分かりやすく解説していきます。
科学的学習法その1ー最強の復習は「思い出す」こと
なぜ、ただ教科書を読み返すよりも、テストをする方が効果的なのでしょうか。それは、学習における最も重要な行為が「想起練習(アクティブ・リコール)」、つまり情報を思い出す作業だからです。
なぜ「テスト」は記憶を定着させるのか
研究によれば、一度学習した内容を、何も見ずに思い出す訓練をすることは、長期記憶を形成するための最も強力な方法です。情報をインプットしただけでは、脳はそれを一時的な情報と判断し、すぐに忘れてしまいます。しかし、テスト形式で「あの知識は何だったかな?」と脳から引き出そうとすることで、脳はその情報へのアクセス経路を強化し、「これは重要な情報だ」と認識します。この努力を伴う想起が、忘れるスピードを劇的に遅くするのです。
今すぐできる想起練習の実践例
ーミニテストを習慣にする 授業や塾で学んだら、その日のうちに、その範囲の簡単な問題集を解いてみましょう。大切なのは、答えを見る前に、自力で思い出そうと必死になることです。
ーブランクページ・テクニック ノートの新しいページを開き、学んだ単元について覚えていることを何も見ずに全て書き出します。その後、教科書と見比べて、抜けていた部分や間違っていた部分を色ペンで書き足します。これにより、自分の理解度が一目瞭然になります。
ー友達と問題を出し合う 休憩時間などに、友達と学んだ範囲から問題を出し合ってみましょう。ゲーム感覚で楽しみながら、効果的な想起練習ができます。
科学的学習法その2ー「孤独な時間」こそが脳を育てる
トップクラスの学生に共通する学習習慣は、他でもない「一人で深く集中する時間」を意図的に確保していることです。この時間は、知識を自分のものにするための聖域と言えます。
なぜ一人の時間が必要なのか
深い学びは、脳に大きな負荷をかける活動です。スマートフォンが近くにある、テレビがついているといった環境では、脳の注意力が分散し、学習内容の処理に使える認知的なリソースが奪われてしまいます。集中できる環境を整え、一度に一つの課題に深く没頭する「ディープワーク」こそが、質の高い学習を実現します。
集中環境を作るための実践例
ー学習空間を整える 勉強する机の上には、その時に使う教材以外は何も置かないようにします。スマートフォンは電源を切って別の部屋に置くのが理想です。
ー時間を区切って集中する 人間の集中力は長くは続きません。「ポモドーロ・テクニック」のように、「25分集中して5分休憩」といったサイクルを繰り返すことで、集中力の質を維持しやすくなります。一度の勉強時間は最大でも90分程度に区切り、リフレッシュを挟むのが効果的です。当塾では1コマ80分授業が基本としています。
ースケジュールに組み込む 「夕食後の19時から21時は、集中学習タイムにする」というように、あらかじめ一人の勉強時間を生活のスケジュールに組み込んでしまいましょう。習慣化することで、勉強を始める際の心理的なハードルが下がります。
科学的学習法その3ー最高のインプットは「教える」こと
自分が学んだ内容を、他人に分かりやすく説明しようとすると、驚くほど自分の理解が深まり、記憶に定着します。これは「プロテジェ効果(教えることによる学習効果)」として知られています。
なぜ教えると理解が深まるのか
人に教えるためには、頭の中にある断片的な知識を、筋道を立てて再構成し、論理的に整理し直す必要があります。このプロセスの中で、「あれ、ここは自分でも曖昧だな」「なぜこうなるんだろう?」といった理解の穴が自然と見つかります。その穴を埋めようとすることで、より深く、より本質的な理解へと到達できるのです。
「教える」学習法の実践例
ーエア授業をしてみる 目の前に生徒がいると想像し、自分が先生になったつもりで、学んだ内容を声に出して説明してみます。数学の公式の証明や、歴史の出来事の因果関係などが効果的です。
ー家族や友達に聞いてもらう 「今日、学校でこんな面白いことを習ったんだけど、ちょっと聞いてくれない?」と、家族や友達に協力してもらいましょう。相手がその分野の素人であればあるほど、より分かりやすく説明する必要があるため、学習効果は高まります。
ー要約を書いてみる 学んだ単元の内容を、短い文章で要約してみるのも良い方法です。要約は、情報の重要な部分を抽出し、再構成する高度な知的作業であり、教える行為と同様の効果があります。
科学的学習法その4ー勉強の成果は「寝ている間」に決まる
徹夜で勉強しても、その知識はすぐに消えてしまいます。なぜなら、学習した内容を整理し、長期記憶として脳に保存する重要なプロセスは、「睡眠中」に行われるからです。
睡眠が記憶を定着させるメカニズム
睡眠中、脳はただ休んでいるわけではありません。日中に学習した内容を海馬から大脳皮質へと移し、神経回路を再編成して記憶を定着させています。特に、学習した直後の夜の睡眠は、その日の学びを定着させる上で極めて重要です。十分な睡眠は、学習効率を上げるための必須条件なのです。
睡眠と休息の質を高める実践例
ー毎日の睡眠時間を確保する 中学生・高校生であれば、最低でも7ー8時間の睡眠を目指しましょう。毎日同じ時間に就寝・起床することで、体内リズムが整い、睡眠の質が高まります。
ー就寝前のスマホをやめる スマートフォンのブルーライトは、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌を抑制し、寝つきを悪くします。就寝1時間前には、スマホやテレビの使用を控え、読書などでリラックスする時間を作りましょう。
ー仮眠やNSDRを活用する 日中に強い眠気を感じた場合は、15ー20分程度の短い仮眠が効果的です。また、横になって目を閉じ、体の各部位に意識を向けてリラックスする「NSDR(ノンスリープ・ディープレスト)」は、仮眠と同様に脳をリフレッシュさせ、午後の集中力を回復させる効果が報告されています。
科学的学習法その5ー「間隔」と「混ぜる」が記憶を盤石にする
効率的な学習の最後の秘訣は、勉強の「タイミング」と「順序」を工夫することです。
間隔を空ける「分散学習」
一度にまとめて長時間勉強する「集中学習」よりも、時間を空けて複数回に分けて復習する「分散学習」の方が、はるかに記憶の定着率が高いことが証明されています。一度忘れかけた頃に思い出すことで、脳はその情報を「生きるために必要な重要な情報」と判断し、より強固に記憶しようとします。
混ぜて解く「インターリービング」
さらに応用的なテクニックが「インターリービング」です。これは、一つの単元の問題ばかりを解き続けるのではなく、あえて異なる単元の問題を混ぜこぜにして解く学習法です。
例えば、数学で二次関数の問題ばかりを1時間解くのではなく、二次関数、図形、確率の問題を20分ずつ、順番に解いていきます。一見、非効率に思えますが、これには絶大な効果があります。脳が問題の種類を「見分ける」訓練をすることになり、テスト本番でどの知識を使えばよいかを瞬時に判断する力が養われるのです。応用力や実践力は、このインターリービングによって鍛えられます。
分散学習とインターリービングの実践例
ー全教科に毎日触れる計画を立てる 特定の教科を一日中やるのではなく、毎日、国語、数学、英語、理科、社会に少しずつ触れる時間割を組みます。これにより、自然と分散学習が実践できます。
ー問題集の解き方を工夫する 問題集を解く際は、順番通りに進めるだけでなく、章をまたいでランダムに問題をピックアップして解いてみましょう。これにより、簡単なインターリービングを体験できます。
まとめ
勉強における「苦しい」という感覚は、必ずしも悪いものではありません。それは、あなたの脳が新しい神経回路を築こうと奮闘している証拠、つまり「成長しているサイン」なのです。
今回ご紹介した5つの科学的学習法ー「想起練習」「集中のための環境設定」「自己説明」「質の高い睡眠と休息」「分散学習とインターリービング」ーは、その努力を確実に成果へと結びつけるための強力なツールです。
これらの方法を日々の学習に意識的に取り入れ、脳の仕組みを味方につけることで、あなたの学習はより効率的に、そしてより確実なものになるでしょう。


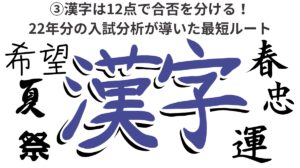
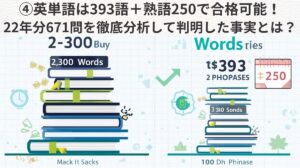
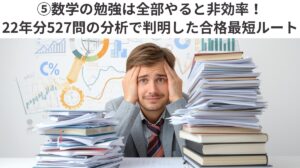
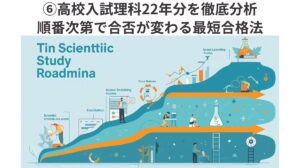


エラー: コンタクトフォームが見つかりません。
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。
無料体験
当塾では、科学的アプローチを活用し、瞑想も取り入れた学習方法を提案しています。ご入会で、瞑想を取り入れた具体的な学習ステップも実践可能です。
無料体験実施中!
お子様の学習効率を飛躍的に向上させたい方、ぜひ無料体験をお申し込みください。
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。